判例を学ぶこと
判例を学ぶことがあります。
実務に直接関係しないこともありますが、関係してくることもあります。
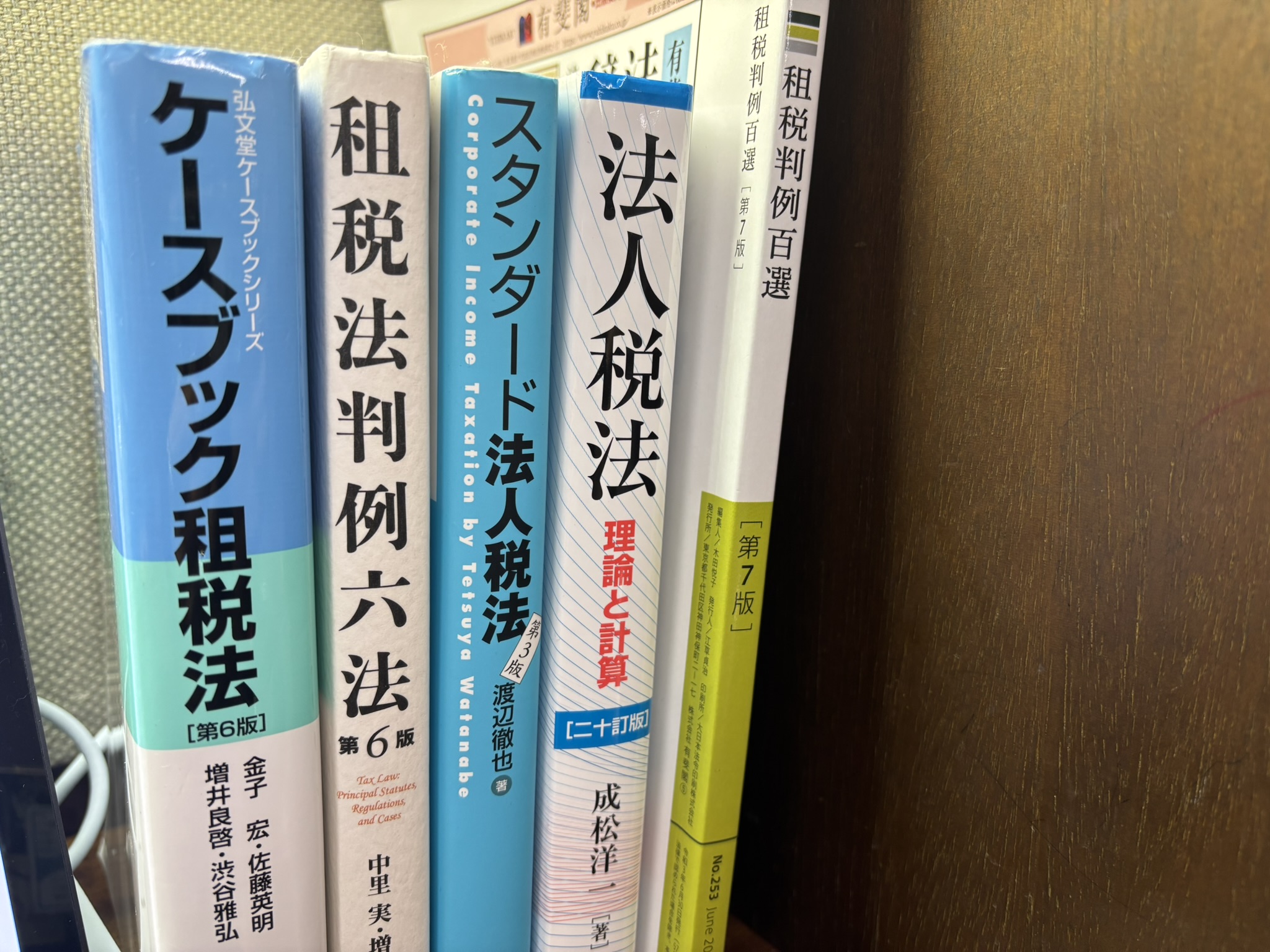
判例に関する書籍は読みごたえがあります…。
判例と税理士実務
税理士の業務は、税理士法という法律にしたっがております。
このため仕事の内容も、その法律の中で決められております。
実務に、法律はどのように影響しているでしょうか。
判例が、実務の中で直接登場することは多くはないかと思います。
税理士が請け負っている仕事の内容によると思いますが、実務の中で直接登場するのは、会計方法や申告書の記入方法なので、裁判例がそのような実務の中で直接関係することは少ないです。
会計方法や申告書の記載方法も、法律で決まっているので、法律が関係していないかという事はありません。
判例を学ぶ意味
法律に全てのことを決めて、条文にすることは難しいです。
全てのことを決められないため、政令や省令、施行令という政府や省庁が決めた内容に記載されたりします。
もっと細かいことは、通達というものに記載されておりますが、通達は法律ではないというのが定説になっております。
しかし通達にしか記載されていない場合には、通達にしたがって業務を行うことになるでしょう。
通達に記載されているが、通達の内容が疑問に感じる場合、法律、法令や通達にも記載されていない場合はどうするか。
その場合には、判例をみることになるでしょう。
判例には、法律や法令などに記載されていない、または判断基準があいまいな場合に裁判となり、その裁判の結果である裁判所の判断が書かれているためです。
判例から判断の感覚を磨く
判例といっても、世の中にはたくさんの判例があり、裁判所の判断が分かれているものもあります。
裁判の結果、法律を直した方がよいと判断されたものは、最新の法律に反映されていることもあります。
しかし、直接反映されていないこともあります。
多くの判例に触れることにより、法律、法令が意味しているところが、少しづつわかるようになってきます。
学者の方ではないので、多くの判例を覚えたり、しっかりとした判断基準を身につけることは到底不可能なことですが、判断基準の感覚を身に付けることはできるかと思い、機会があれば判例に触れるようにしております。
そうは言っても、判例を読み込むこと自体、簡単ではありませんので、やすやすとできるものではありませんが…。