賦課(ふか)と配賦(はいふ)
日本語の意味としては同じであっても、厳密には異なる場合もあります。
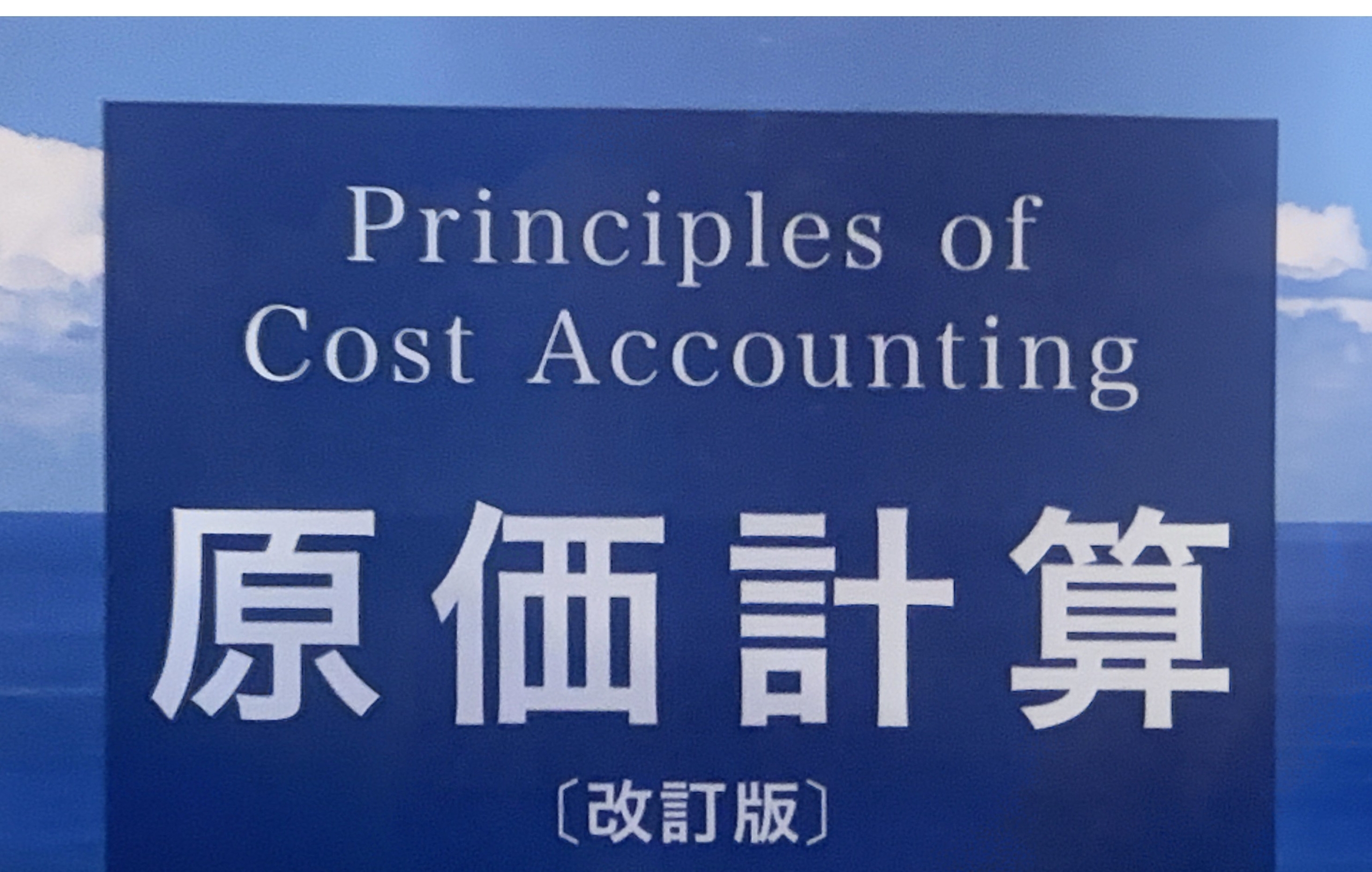
実務では一見、どちらでもよいような気がしますが…。
賦課と配賦
「賦課」(ふか)と「配賦」(はいふ)には、どちらも割り当てるという意味があります。
日常ではあまり使用しない言葉と思いますが、会計の世界、特に原価計算の世界では
よく使用される言葉です。
どのように使われるでしょうか。
原価計算の世界では
原価計算とは、製造業の経理で使用される計算で、製造する製品の原価(元の値段)が
いくらであるかを算定する際などに使われる計算手法(考え方)です。
製品の原価には、直接費と間接費のふたつの費用があります。
直接費とは、製品を作るための材料費や、製造を行っている方たちの賃金などをいいます。
一方、間接費とは、製品を作る工場の電気代やガス代、事務員の方たちの給料などを
いいます。
製品の原価を計算するときに、これらの直接費と間接費の費用を割り当てるさいに、
「賦課」と「配賦」という言葉が出てきます。
直接費で使われるのが「賦課」で、間接費で使われるのが「配賦」になります。
直接費を製品の原価に割り当てる → 「賦課」
間接費を製品の原価に割り当てる → 「配賦」
原価計算では、厳密には「賦課」と「配賦」の意味は異なっております。
間接費の場合には直接費用の割り振りができないため、ある一定の基準にしたがって、
割り振りをすることから、直接費と同じ「賦課」ではなく、「配賦」という言葉を
使っております。
間違って使った場合
日常の経理部の中での会話において、賦課と配賦を誤って使っても、
通常は問題にはなりません。
だいたいの意味が通じればよいでしょうし、その使い方を誤ることで、
会計の計算結果が異なるかというと、その確率は大変低いでしょう。
ところが、学者の方々において、この使用を誤ると大きな問題となります。
そもそも意味が異なっておりますので、誤用してしまっては、
本来意図した内容と変わってしまいますので、大きな問題になるはずです。
いずれにせよ、一般の実務においては間違って使用しても、何も影響はありませんが、
違いを知っておいても損はないでしょう。