デリバティブ取引の仕訳
デリバティブ取引の仕訳、と聞くと難しいと考えてしまいます。
仕訳自体はそれほど難しいものではありません。
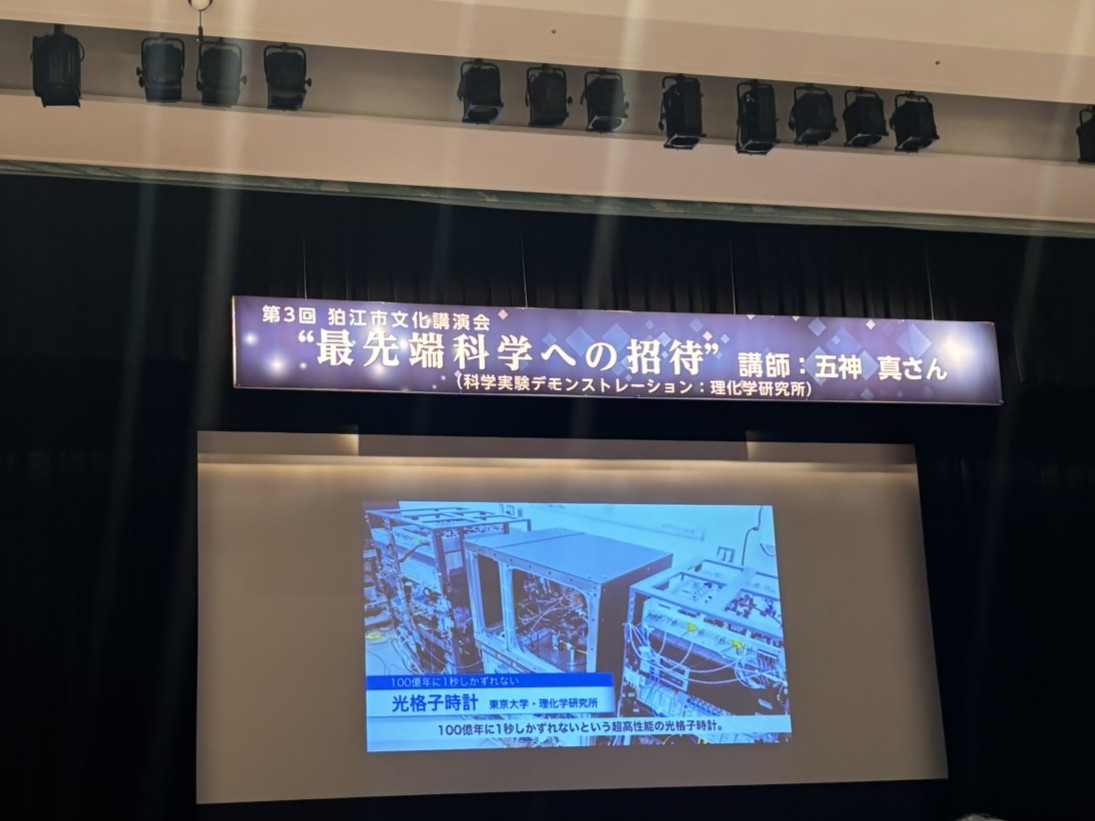
聞きなれない言葉はなんでも難しく感じてしまいます。
デリバティブ取引
デリバティブ取引とは、金融派生商品のことをいいます。
はじめてデリバティブ、金融派生商品という言葉を聞いた時には、何のことか全く理解できませんでした。
恐らく、一般の人には関係のない世界での話なのだろう、とその時は思いました。
金融派生商品とは、先物取引、オプション取引などの特殊な取引のことをいいます。
この中には、為替予約も含まれます。
いずれにせよ、なにか難しそうな感じがして、言葉だけ聞いてもよくわかりませんでした。
取引を理解できれば難しくない
ある実務も理論もよくご存じの簿記の高名な講師の方がおっしゃっておりましたが、簿記は取引を理解すべきで、仕訳で理解すべきではないとおっしゃっておりました。
単に仕訳を覚えたところで、取引を理解できていなかったら、応用がきかないので、試験においても実務においても、対応できないとのことでした。
確かに一理あります。
予備校の税理士試験対策の講義などでは、仕訳を覚えて、パターンで対応するように言われます。
問題を繰り返し問いて、このパターンの問題では、このパターンの仕訳を当てはめる、という感じです。
最初の頃は、この方法で行なえば、点数が伸びますが、応用期に入ると、途端に点数が伸び悩みます。
取引内容がわかっていないため、応用がきかないのです。
金融派生商品においては、先物取引が典型的な例なので、この取引から覚えると良いとのことです。
(先の講師の方の受け売りですが…)
先物取引とは、将来に発生する取引を現在の時点で契約する取引になります。
例えば、将来、200円で大豆を売る約束をして、その後、その大豆の値段が180円に下がったので、大豆を買うことで決済すると、20円の利益になります。
大豆の将来の価格が読めていれば、もうけることができますが、将来の価格が読みにくいため、投機性がある、すなわち損をする可能性も高いといわれます。
基本の仕訳は2パターンだけ
契約をしたときには、仕訳はありません。
証拠金を先物取引を扱う会社に支払うため、その金額の仕訳が発生します。
(借方)先物取引差入証拠金(貸方)現金預金
決算日には時価で評価します。
売る契約をしていて、決算日に価格が下がっていると、その分は有利になっていることから、益を計上します。
逆に価格が上がっていると、損を計上します。
基本的には、仕訳は決算日の決済日の2パターンだけです。
★決算日
益が出た場合は次の仕訳です。
(借方)先物取引資産(貸方)先物取引損益
損が出た場合は次の仕訳です。
(借方)先物取引損益(貸方)先物取引債務
決算日翌日には、振替仕訳で元に戻します(振替しない場合もあります)。
★決済日
最終的に決済をして、利益が出た場合には、次の仕訳になります。
(借方)現金預金(貸方)先物取引損益
損が出た場合には、次の仕訳になります。
(借方)先物取引損益(貸方)現金預金
同時に証拠金を戻す仕訳が発生します。
(借方)現金預金(貸方)先物取引差入証拠金
難しそうな割には、取引も仕訳もシンプルです。
益が出るか損が出るかは、売る契約(売り建てともいいます)の場合には、値段が下がれば、その価格で買うように決済すると益になります。
売りを売り上げ、買いを仕入と考えると、売りが買いよりも高いと得になるということで覚えやすいかと思います。
売りが買いよりも低いと損になります。
まさに取引をイメージすると、わかりやすくなります。