通関士試験の合格までにおこなったこと(その2)
通関士試験を受けるために、セミナーを受講しました。
それがなければ受験開始から1年で合格はできませんでした。
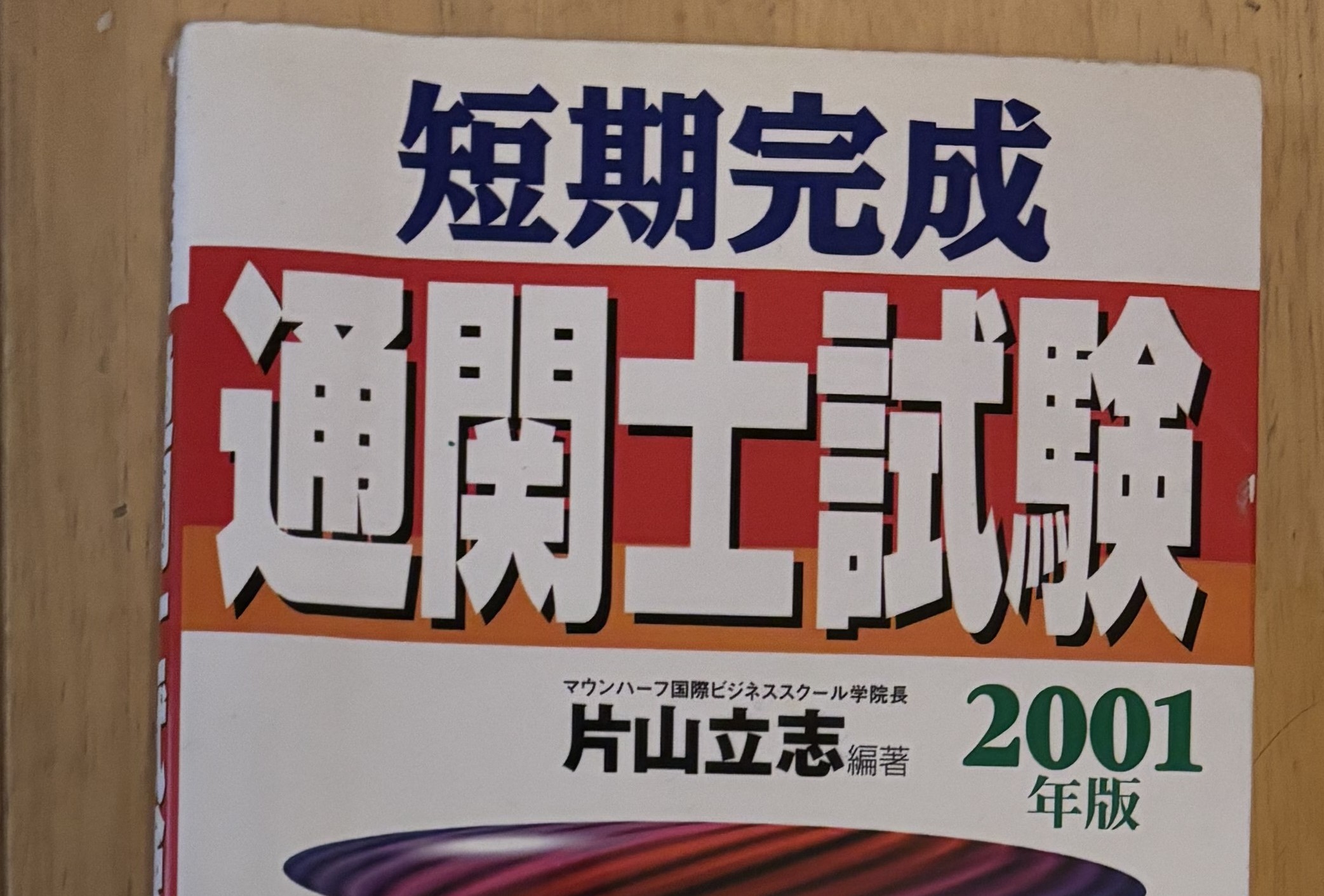
まずはここから始めました…。
セミナーの内容
先のブログからの続きとなります。
セミナーの講師は、マウンハーフ社の多くの本の著者である片山立志先生本人でした。
まさか片山先生から直接教えて頂けるとは思っておりませんでしたので、
とても幸運でした。
あとからわかったことなのですが、片山先生は通関士試験対策を初めておおやけに
行なったその道の開祖ともいえる方でした。
このため講義の内容も、それまでの経験に基づいた通関士試験に出題されるポイントに
しぼったものであり、通関に関して全くの素人だった私でもわかるようなものでした。
ひたすら勉強
通関士試験は、輸入申告書の作成のような実際の業務にかかわる内容だけではなく、
関税法や関税定率法などの法律の知識について問われます。
このため、暗記を行うことが多く、ひたすら法律の内容を覚える学習をおこないました。
教科書としては、セミナーで主に使われていたマウンハーフ社の通関士ハンドブックを
メインとして覚えましたが、通関実務をまったく行ったことがない私にとっては、
つらい学習でした。
片山先生のセミナーでは、こうした実務経験のない人も対象としていたためか、
ゴロを使って覚えることもありました。
その他には、片山先生が統計品目を歌にして、そのCDを受講者に配布したことも
ありました。
統計品目は、輸出入に使用されるコードで、輸出入される品物の種類を数字で分類している
コードなのですが、数字と品物の関連性がないため、覚えるのには苦労しました。
しかし歌で覚えることで、比較的あっさりと覚えることができました。
それでも通勤電車の中では、教科書と講義で取ったノートは肌身離さず持ち歩き、
いつも電車で覚えた内容を、歩いているときに思い出すという作業を1年間近く
繰り返しました。
何とか合格
マウンハーフ社のセミナーでは模試もおこなっており、試験日に近づいてくると
定期的におこなわれました。
勉強の甲斐があってか、最初の全くできなかったテストも、最後の方の模試では
だいぶ得点できるようになりました。
そして本番の試験を迎えましたが、模試で想定していた内容が出題され、
予想以上に早く回答でき、答案の見直しを含めて、終了時間の10分前には
解き終わりました。
試験終了10分前までであれば試験会場から退出できるのですが、10分前ぎりぎりに
終了したことを知らせるための手を挙げたため、試験官の方に注意されましたが、
何とか試験会場から退出させてもらえました。
早く終わりすぎたので、逆に不合格かと思いましたが、何とか合格できておりました。
官報に合格者名が掲載されたとき、1年間の勉強がむくわれ、とてもうれしかったのを
覚えております。
通関士試験は最難関の試験ではありませんが、合格率が10%~20%の
試験であることから、独学で乗り切るのは厳しいでしょう。
私としては通学の講座をおすすめしますが、2025年現在、マウンハーフ社では残念ながら
通学講座を行なっていないようです。
通信講座は引き続き行っているようですので、通信講座で片山先生の講義を受講するか、
他の会社が主催する通学講座を試してみるのも、良いのではないでしょうか。